ストライク集計のM&A件数とMARRの件数の違い

ストライク(M&A Online)が集計、分析した2019年7-9月期のM&Aに関する記事です。以下に掲載しています。
3年連続で四半期200件超え、ということです。
1-9月累計で602件ということですが、本誌がいつもお伝えしている年間3,500−4,000件というデータを大きく食い違うことに気づかれた読者もいらっしゃると思います。
本誌がよく参照しているM&AのデータはMARR online(https://www.marr.jp/)をもとにしています。
MARR onlineのデータ(https://www.marr.jp/genre/graphdemiru)によると、2019年1-9月でのM&A件数は3,000件を超えています。
600件と3,000件の差の原因を探っておきましょう。
ストライクの602件は、上場企業の適時開示情報のうち、経営権の移転を伴うM&A(グループ内再編は除く)という条件がついています。
それを考慮すると、
1)上場会社以外のM&A
2)経営権の移転を伴わないM&A
がMARRには含まれおり、これが2,400件の差になっているはずです。内訳はわかりませんが、毎月MARRを購読していると、明らかに2)経営権の移転を伴わないM&Aも増えてきています。私は経営権の移転を伴わないM&Aから経営権の移転を伴うM&Aへ移行した成功例として、ドンキによるユニーの買収をあげています。機会があればあらためてこの買収についてもとりあげてみたいと思います。
データの読み方として、年間4,000件の中には、経営権の移動を伴わないM&Aも結構な割合で含まれているということを知っておくべきでしょう。MARRを定期購読していますが、かなりの割合で経営権の移転を伴わない(たとえば5%程度の出資など)の案件が掲載されています。そして、もちろん上場企業が関係しないM&Aも一定以上存在します。
周りがやっているからやる、ということではもちろんありませんが、経営権の移転を伴わないM&Aで少額投資をし、実際にビジネスを一緒にやって、成果を出してから買収をする、うまくいかなかった場合には買い戻しをする、というやり方も買い手は検討すべきです。
**
■7~9月期、3年連続で200件超え、1000億円超は5案件
2019年第3四半期(7~9月期)のM&Aは前年同期比14件減の208件だった。同四半期として200件を超えるのは3年連続。上期を含めた1~9月期でみると、合計602件で、2009年以来10年ぶりの600件台に乗せた。日銀による金融緩和が引き続きM&A市場の活況を後押ししており、海外での大型企業買収も相次いだ。
上場企業の適時開示情報のうち、経営権の移転を伴うM&A(グループ内再編は除く)について、M&A仲介のストライク(M&A Online)が集計した。
7~9月期のM&Aの総開示件数208件のうち、日本企業がかかわる海外案件(買収のほか、売却、日本企業がターゲットになる場合を含む)は49件とほぼ4分の1を占める。M&Aをテコにグローバル展開を加速している様子がうかがえる。
取引金額が1000億円を超える大型案件は5件。1000億円超の案件は今年に入り9月末までに11件あるが、第3四半期だけでほぼ半数を占めた。
最大案件はアサヒグループHD
日本企業によるM&Aで今年最大となったのが豪ビール大手のカールトン&ユナイテッド・ブルワーズ(CUB)を約1兆2000億円で買収するアサヒグループホールディングス(HD)の案件。酒類事業の買収としては2014年にサントリーホールディングスが米ウイスキー大手のビームを約1兆6000億円で傘下に収めたのに次ぐ規模となる。
CUBはビール世界最大手アンハイザー・ブッシュ・インベブ(ベルギー)の子会社。アサヒはCUBの販路を活用し、「スーパードライ」など主力商品の売り上げ拡大を目指す。
今年のM&A市場で最大の“サプライズ”となったのが国内最大級の衣料通販サイト「ゾゾタウン」を運営するZOZOを子会社化するヤフー(10月1日にZホールディングスに社名変更)の案件。EC(電子商取引)事業で先行するアマゾン、楽天を追撃するのが狙いだ。
TOB(株式公開買い付け)を通じて50.1%株式を取得する。買付金額は4007億円。ZOZO創業者で前社長の前澤友作氏は約37%の保有株式のうち30%強についてTOBに応じる。
これに続くのが東京センチュリーの案件。約3200億円を投じて、米国の航空機リース大手、アビエーション・キャピタル・グループ(ACG)の買収を決めた。株式75.5%を追加取得し、完全子会社化する。
ユニゾへのTOBにも注目
帰趨が注目されているのが不動産・ホテル業のユニゾホールディングスの子会社化を目的とする米投資会社フォートレス・インベストメント・グループのTOB。旅行大手エイチ・アイ・エスの敵対的TOBに対抗し、フォートレスはユニゾ経営陣の賛同を得たホワイトナイト(白馬の騎士)として参戦した。買付金額は最大1368億円。
しかし、9月末、ユニゾはこのTOBへの賛同を撤回した。一方、フォートレスはTOB期間をすでに3度延長(11月1日まで)し、全株式の3分の2超の応募がないと不成立となる。さらに米投資会社のブラックストーンが対ユニゾTOBに名乗りを上げる意向を示し、混迷の度が一段と深まっている。
2019年7~9月M&A 取引金額上位15傑
1 アサヒグループホールディングス、豪ビール大手カールトン&ユナイテッド・ブルワリーズ(CUB)を子会社化(約1.2兆円)
2 ヤフー、衣料品通販サイトのZOZOをTOBで子会社化(4007億円)
3 東京センチュリー、米航空機リース大手のアビエーション・キャピタル・グループを子会社化(3213億円)
4 米フォートレス・インベストメント・グループ、ユニゾホールディングスをTOBで子会社化(1368億円)
5 DIC、独化学大手BASFの顔料事業を買収(1162億円)
6 住友化学、豪農薬大手ニューファーム傘下の南米4社を子会社化(約700億円)
〃 三菱商事、持ち分法適用関連会社の千代田化工建設を子会社化(700億円)
8 大阪ガス、米シェールガス開発会社のサビンを子会社化(約650億円)
9 サンデンホールディングス、流通システム事業子会社のサンデン・リテールシステム(群馬県伊勢崎市)を投資ファンドのインテグラルに譲渡(500億円)
10 レンゴー、産業用重量物包装メーカーの独トライコー・パッケージング&ロジスティクスなど2社を子会社化(約323億円)
11 エア・ウォーター、産業ガス大手の独リンデからインド事業を取得(約204億円)
12 ネクソン、スウェーデンのゲーム開発スタジオEmbark Studiosを子会社化(約104億円)
13 ワコールホールディングス、米の女性インナーウエア企画販売会社Intimates Onlineを子会社化(91.8億円)
14 クリエイト・レストランツ・ホールディングス、米イタリアンレストラン「イルフォルナイオ」を子会社化(80.5億円)
15 横浜インポートマート、「横浜ワールドポーターズ」運営の横浜インポートマート(横浜市)を子会社化(70億円)
93%が満足と回答したファイナンスドリブンキャンプ
本講座では、短期間でCFO(最高財務責任者)への第1歩を踏み出すことを目指します。大量の決算書に触れ、大量にアウトプットし、大量のフィードバックを通してファイナンスという武器を手に入れられます。ブログでは話せない「ライブ講義」も充実しています。まずは無料説明会を受講してみて下さい。
本誌について
本誌は、M&Aを売り手、買い手、アドバイザーが三方良し、となるのが当たり前の世界の実現を目指しています。そのためには当事者が正しい情報を得て、安心して相談のできる場が必要です。その実現に向けて本誌は、日本M&Aアドバイザー協会で、以下のサービスやセミナーを提供しております。
| M&A仲介・アドバイザーを事業としたい方・既にされている方へ | |||
|---|---|---|---|
| セミナー・サービス名 | 詳細 | 金額 | 時間 |
| 誰にでもわかるM&A入門セミナー | ・会場開催の詳細とお申込み ・オンライン講座の視聴 |
無料 | 2時間 |
| M&A実務スキル養成講座 | ・会場開催の詳細とお申込み ・オンライン開催の詳細とお申込み ・M&A実務スキルの詳細 |
198,000円 | 2日間 |
| JMAA認定M&Aアドイザー資格取得およびJMAA会員に入会 | ・資格詳細とお申し込み | 入会金33,000円 月会費11,000円(1年分一括払) | - |
| 案件サポート制度 | JMAA会員が初めてM&Aアドバイザリー業務に取り組む場合、あるいはすでに何度かアドバイザリー業務に経験があっても、難易度が高い案件の場合のための、JMAA協会が会員に伴走して案件成約に向けて協力する制度です。 お申し込みは当協会ご入会後にお知らせします。 | JMAA正会員の関与する対象案件の成功報酬の50% | - |
| 買収を検討されている企業団体様へ | |||
| セミナー・サービス名 | 詳細 | 金額 | 時間 |
| 誰にでもわかるM&A入門セミナー | ・会場開催の詳細とお申込み ・オンライン講座の視聴 |
無料 | 2時間 |
| M&A実務スキル養成講座 | ・会場開催の詳細とお申込み ・オンライン開催の詳細とお申込み ・M&A実務スキルの詳細 |
198,000円 | 2日間 |
| 買い手様向けセカンドオピニオンサービス | ・M&Aセカンドオピニオンサービスの詳細 | 33,000円 追加相談サービス 33,000円/1時間 | 1時間〜 |
| 売却を検討されている企業団体様へ | |||
| セミナー・サービス名 | 詳細 | 金額 | 時間 |
| 誰にでもわかるM&A入門セミナー | ・会場開催の詳細とお申込み ・オンライン講座の視聴 |
無料 | 2時間 |
| M&A実務スキル養成講座 | ・会場開催の詳細とお申込み ・オンライン開催の詳細とお申込み ・M&A実務スキルの詳細 |
198,000円 | 2日間 |
| 売り手様向けセカンドオピニオンサービス | ・M&Aセカンドオピニオンサービスの詳細 | 33,000円 | 1時間〜 |

M&A実務を体系的に学びたい方は、M&A実務スキル養成講座
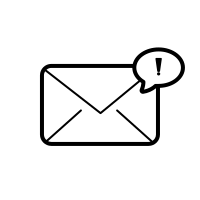
メルマガ登録はこちら
ファイナンスドリブンキャンプ
生成AIキャンプ

大原達朗の経営リテラシー-自ら考え、行動しよう-
